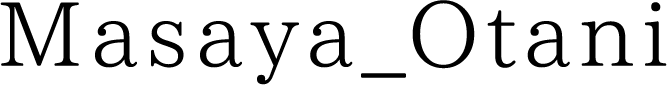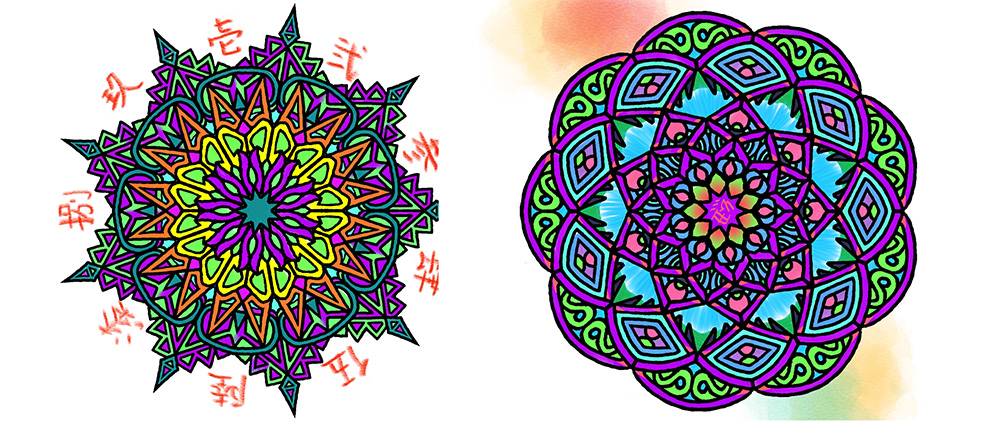精神医学は、シンギュラリティに間に合うのか
――当事者として未来を考えるということ
ある日、立川談志の落語をYouTubeで流しながら、1968年の星新一のエッセイを読んでいた。
どちらもこの世を去って久しい。けれど、耳と目を通して届く言葉の響きに、ふと「死者の声と会話しているようだ」と思った。
少し陳腐な表現かもしれない。でも、この感覚はきっと、古典に触れる人なら誰しも味わったことがあるのではないだろうか。
死者の言葉と現在が重なる感覚。
あるいは、未来の自分に手紙を届けるような感覚。
技術は進化する。では、心の治療は?
僕は未来のことをよく考える。とくに、技術と医療がどこまで進化するのかに関心がある。
2045年、人工知能が人間の知能を超える「シンギュラリティ」が起こるといわれている。
テクノロジーが日々進化する今、それはまったく荒唐無稽な話とは思えない。
けれど、そのときまでに――
僕の心の病は治っているのだろうか?
治らないまま、生きている
僕は、双極性障害(躁うつ病)とADHDの診断を受けている。
これまで十年以上、薬を飲み、生活を調整し、何度も再発を繰り返してきた。
現在も、処方された薬を飲んでいる。
けれど、劇的な改善を実感することは少ない。
気分の波、過集中、倦怠感、不眠。
日常の中で襲ってくるそれらを、ただ静かに受け止めながら暮らしている。
精神科の薬は、風邪薬のようにはいかない。
「飲めば治る」ではなく、「飲み続けるしかない」ことに、絶望を感じる瞬間もある。
精神医学が追いついていないと感じるとき
テクノロジーは急速に進歩している。
医療機器、ゲノム編集、ナノマシン、AI診断――。
それに比べて、精神医学はどうだろう。
今なお、投薬と対話療法が中心であり、根本的な治癒が難しいことが多い。
双極性障害やADHDのような「慢性的かつ個別性の強い疾患」においては、なおさらそう感じる。
精神の不調は、構造的に「人格の一部」と結びついている。
それを“治す”とはどういうことか。
そもそも人格を、医学的に書き換えることはできるのか。
医療の限界に直面するたび、僕はこうした問いを抱える。
小さな方法を、未来に向けて続けていく
完治が望めないとしても、「少しでも楽に生きる方法」はある。
僕が見つけたのは、体内時計を整えることだった。
決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。
たったそれだけで、感情の波が和らぐことがある。
不安が少し軽くなることがある。
最近では、瞑想も取り入れている。
呼吸に意識を向けるだけで、内側のざわめきが静まる時間がほんの少しだけ訪れる。
それだけでも、意味があると思えるようになった。
「まだ完全ではないけれど、生きていく術を、自分の中につくっていく」
これが、僕なりのセルフコントロールであり、未来の精神医学への希望でもある。
人工知能が人間を超えるそのとき
シンギュラリティが到来すれば、自己を模倣したAIが存在する未来が現実になるかもしれない。
僕の声や記憶や思考の癖を持った人工知能が、僕の代わりに誰かと会話を続けてくれるかもしれない。
けれど僕が本当に望むのは、**「苦しみを理解してくれる存在が増えること」**だ。
完全に治らなくても、共に生きていける。
不完全なままでも、否定されない。
そんな社会や医療に向かって、自分の体験と言葉が何かの“橋”になればいいと思っている。
終わりに
この文章は、2018年に初めて書いた原稿を、2025年の視点で書き直したものです。
当時と今とでは、少しだけ見えているものが違います。
でも、ひとつだけ変わらないのは、
「生きづらさを抱えながらでも、未来を考えていたい」
という僕自身の願いです。
もし、あなたの未来にも届く言葉があったなら、
それはきっと、同じ時代を生きている証なのだと思います。